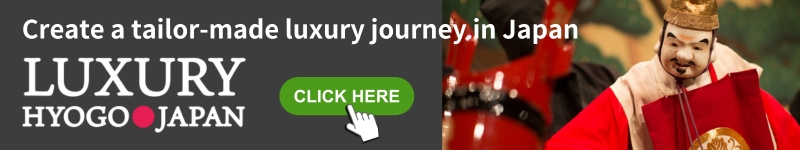- 自然・風景
- 歴史・文化
- グルメ
- 体験
No.f_0034
瀬戸内から播磨へ――塩と醤の発酵物語
瀬戸内の穏やかな海を渡ると、そこには塩と醤(ひしお)が織りなす物語が広がる。江戸時代、赤穂の塩を積んだ船は潮待ちの港を経て小豆島へとたどり着いた。良質な塩はやがて大豆や小麦と結びつき、温暖な島の気候のもとで発酵を重ね、小豆島の醤油づくりが始まったのである。「醤のさと」と呼ばれる島には、400年以上前から受け継がれ、今もなお木桶で仕込まれる濃口醤油の香りが漂っている。
その後、播磨の城下町・兵庫県龍野では、京料理に欠かせない繊細な色合いを求め、淡い色合いながら旨みを閉じ込める「淡口(うすくち)醤油」が生まれた。
こうして日本食に深い香りと旨味を与える発酵調味料は、その土地の気候風土と職人の手仕事によって、長い時間をかけて育まれてきた。兵庫県の良質な塩や大豆から生まれる醤油や味噌の文化をめぐり、さらに瀬戸内海を渡って伝統的な醤油作りで知られる小豆島を訪ねるこの旅は味覚だけでなく香りや手ざわりまでも、日本の発酵文化の奥深さを五感で堪能するひとときとなる。
淡口醤油の里、龍野
 一級水系の揖保川
一級水系の揖保川
神戸空港から車でわずか1時間半ほどの兵庫県南西部、播州平野を流れる揖保川沿いに、淡口(うすくち)醤油の里、龍野がある。1587年、地元の藩主たちが醤油作りを奨励し、地域の産業として発展させた。播州平野の豊かな大豆や小麦、米、揖保川の清らかな水、そして瀬戸内海の赤穂の塩といった良質な原料に恵まれ、淡く香り高い「淡口醤油」が生み出された。さらに、揖保川を活用した輸送ルートにより、新鮮な醤油は食文化の先進地である京都や大阪などへも届けられ、その評判は早くから広まった。

 旧醤油工場の煙突
旧醤油工場の煙突
代々続く町屋や醤油蔵が立ち並ぶこの地区は、たつの市龍野重要伝統的建造物群保存地区として大切に残されている。石畳の通りを歩けば、白壁の軒先からほのかに醤油の香りが漂う。
 觜﨑屋(はしさきや)本店(和菓子屋)
觜﨑屋(はしさきや)本店(和菓子屋)
 名物「醤油まんじゅう」(左)。隣は斑古(はんこ)ささげという希少な特産豆を使って作られる「煉羊羹」で、贈答品にもおすすめの上品な和菓子。
名物「醤油まんじゅう」(左)。隣は斑古(はんこ)ささげという希少な特産豆を使って作られる「煉羊羹」で、贈答品にもおすすめの上品な和菓子。
創業約300年の和菓子屋「觜崎屋本店」には、名物の醤油饅頭がある。小豆を炊いて仕込んだ自家製餡を、たつの名産のうすくち醤油を練り込んだ皮で包んで蒸したふわふわのお饅頭。ほんのりとしょうゆが香り、お土産でも人気の一品だ。

この町には、手仕事を守り続ける地元の人々の営みが、今も静かに息づいている。
醤油の世界を五感で体験

左から、濃口醤油、淡口(うすくち)醤油、たまり醤油、再仕込醤油、白醤油
白壁の通り沿いに佇む「発酵Lab Coo(発酵ラボクー)」では、醤油の世界を五感で体験できる講座が受けられる。
日本の食文化を支えてきた醤油は、大きく分けて5種類に分類される。その品質は、原料や発酵方法、塩分濃度などを基準とするJAS規格(日本農林規格/Japan Agricultural Standards)によって厳しく管理され、審査会では蛇の目模様の利き味皿を用いて、色・香り・味わいが丁寧に確かめられている。
日本では醤油をワインのように捉え、料理とのペアリングを考える文化がある。たとえば、左から2番目の淡口(うすくち)醤油は、淡い色合いと軽やかな香りが特徴。素材の色や風味を生かしつつ、全体をそっとまとめる名脇役。少量でもだしの旨味と塩味を引き出すため、上品で低塩の料理に仕上げたいときに重宝される。
一方、熟成期間の長いたまり醤油や再仕込み醤油は、濃厚で複雑な味わいが魅力。脂身のある肉料理や照り焼きのようなコクを出したい料理で真価を発揮する。
 左から、仕込み中の醤油、生醤油、赤穂の塩、播州平野の小麦、西播磨の大豆
左から、仕込み中の醤油、生醤油、赤穂の塩、播州平野の小麦、西播磨の大豆
龍野で生まれる淡口醤油は、西播磨・三日月地域の大豆、播州平野の小麦、赤穂の塩、揖保川の軟水といった地元の豊かな恵みを原料に、職人の手仕事と長い発酵・熟成の時間をかけて丁寧に作られる。
世界で一つだけの”MY醤油”作りに挑戦

 スパイスを瓶へ追加していく
スパイスを瓶へ追加していく
醤油蔵の町だからこそ手に入る、しぼりたての生醤油で、世界に一つだけの「MYしょうゆ」を作る。選べるブレンドの種類は、「和のだし醤油」「山椒醤油」「香味醤油」「ハーブ醤油」「スパイス醤油」の5種類のうちの1種類。女性に人気のハーブ醤油なら、昆布、にんにく、鷹の爪、ローズマリー、バジルを加えていく。
天然だしやスパイスを自分好みで量を変え、ブレンドすると香りがぐっと立ち上がる。
 もろみを搾った後に、火入れをせずにろ過のみを行った生醤油は、一般に流通することが少なく、醤油蔵の直売所などで手に入る。
もろみを搾った後に、火入れをせずにろ過のみを行った生醤油は、一般に流通することが少なく、醤油蔵の直売所などで手に入る。

 体験料は1人につき2,200円で、「MYしょうゆ」1本付き。申し込みは電話または公式LINEから。
体験料は1人につき2,200円で、「MYしょうゆ」1本付き。申し込みは電話または公式LINEから。
加熱したあとボトルを密封し、和紙に筆で書いたラベルを添えれば、MY醬油が完成。味わいだけでなく、香りや自分だけの創作の喜びまで、五感で楽しめる特別な体験だ。
自分だけの味を作る、みそ玉体験
 カラフルなみそ玉は見るだけでも楽しめる。
カラフルなみそ玉は見るだけでも楽しめる。
醤油と並び、日本の暮らしに欠かせない発酵食品が「味噌」。その味噌にかつお節やだし、具材を合わせ、1食分ずつ丸めたものが、みそ玉。お湯を注ぐだけで手軽にお味噌汁が楽しめる、便利でアイデアあふれる一品だ。
発酵Lab Coo では、日本が誇る発酵文化を広く伝えたいという思いから、醤油に限らず麹、味噌、甘酒作りのプログラムを実施している。そのうちの一つが、みそ玉作り。見た目に可愛いだけでなく、お湯を入れて簡単に美味しい味噌汁ができるため、若い女性にも人気のプログラムだ。
 トッピングは、青のり、ごま、油揚げ、とろろ昆布、カレー粉など
トッピングは、青のり、ごま、油揚げ、とろろ昆布、カレー粉など
糀をたっぷり含んだ播州味噌に、天然乾燥野菜を加え、好みのトッピングを施せば、オリジナルのみそ玉が完成する。
 1個で1人分の味噌汁ができる。トッピングによって風味の違いを楽しめる。
1個で1人分の味噌汁ができる。トッピングによって風味の違いを楽しめる。
日本人にとって、味噌汁はソウルフード。食卓に欠かせない存在であり、季節や地域の食材を巧みに取り入れた、地域の食文化を映す鏡でもある。みそ玉は、そんな伝統の知恵と味をぎゅっと詰め込んだ手軽な保存食。発酵Lab Cooでのみそ玉作り体験で、日本の食文化を体感してもらいたい。
 栄養士の松下美幸さんと、発酵や醤油を研究する農学博士であるご主人の裕昭(ひろあき)さんが発酵インストラクター
栄養士の松下美幸さんと、発酵や醤油を研究する農学博士であるご主人の裕昭(ひろあき)さんが発酵インストラクター
 自家製の麹で作る黒麹甘酒と白い甘酒(ともに500円税込)
自家製の麹で作る黒麹甘酒と白い甘酒(ともに500円税込)
ご夫婦で営む発酵教室には、レッスンだけでなくカフェも併設されており、手作りの発酵食品や甘酒をゆったりと味わうことができる。
たつの町の宿泊の予約
国内最大級の木桶で仕込む蔵元へ

 年季の入った吉野杉の木桶で熟成させる
年季の入った吉野杉の木桶で熟成させる
たつの市から車で北へ約1時間、山々に囲まれた自然豊かな多可町の里山に、1889年創業の足立醸造がある。創業以来、木桶仕込みの伝統を守り続け、職人たちは多い時には週3日もろみを入念にかき混ぜ、発酵を見守る。100年以上使い続けられた木桶の中で1年以上熟成された醤油は、乳酸菌や酵母菌が棲み着いた蔵独自の香りと深い旨味をまとい、足立醸造ならではの味わいを生み出す。
 贅沢に仕込まれた丹波篠山の黒大豆
贅沢に仕込まれた丹波篠山の黒大豆
足立醸造では、国産原材料の中でも有機JAS認証(オーガニック認証)を取得したものを主に使用している。
添加物を加えず、昔ながらの木桶仕込みの製法でじっくりと醸すことで、安心・安全な醤油が生まれるのだ。ここで育まれるのは、オーガニックにこだわったまろやかな醤油や、丹波篠山の黒豆を使った濃厚な醤油など、兵庫の土地が育んだ個性豊かな味わい。たつのの淡口醤油とはまた異なる香りとコクに触れることで、地域ごとの風土が醤油の味に映し出されることを実感できる。

2018年、1本約5,000L仕込むことができる木桶を4本新調した。国産有機原材料に特化し、一年以上自然のままに発酵・熟成していく。
 契約農家が育てた原材料で仕込む、100%オーガニックの有機JAS認証醤油
契約農家が育てた原材料で仕込む、100%オーガニックの有機JAS認証醤油
 足立 学(まなぶ)さんは広告業からの転身
足立 学(まなぶ)さんは広告業からの転身
蔵の一角に据えられた大きく新しい木桶は、全量を木桶仕込みで仕上げるという強いこだわりから、2012年に職人の手で組み立てられた。今では希少な伝統製法である木桶仕込み。その130年の歴史を守りながらも、洗練された蔵の姿を支えるのは、5代目の足立学(まなぶ)さんと兄の裕(ゆたか)さんだ。「若い職人たちを積極的に迎え入れ、どんどん新しいことに挑みたい」と学さんは語る。長い年月をかけて育まれた木桶の発酵の香りと、兄弟の情熱が響き合う蔵の空気は、訪れる人に兵庫の発酵文化の奥深さと、希望に満ちた未来を感じさせる。
多可の宿泊の予約
赤穂の恵みから生まれた醤油の里・小豆島


姫路港からフェリーに乗り込み、瀬戸内の穏やかな海を渡ること約100分。船上からは家島諸島の点在する島々が望め、時折カモメが並走する姿に旅情がかき立てられる。
やがて視界に現れるのは、オリーブと醤油の島・小豆島。港に近づくと、白壁の町並みや緑豊かな山々が迎えてくれる。
江戸時代、赤穂の良質な塩を積んだ船は瀬戸内の潮待ち港を経て小豆島へと渡ったとか。温暖な気候と清らかな水に恵まれた島で、赤穂の塩は大豆や小麦と結びつき、やがて醤油づくりが始まった。
400年以上の歴史を持つ小豆島の醤油は、今もなお杉の大桶で仕込まれ、時間とともに深い旨味と香りを育んでいる。島の通りには木桶の並ぶ醤油蔵が軒を連ね、「醤の郷(ひしおのさと)」と呼ばれる独特の風景が広がる。
 見学自由のヤマロク醤油の蔵は、明治初期に建てられたもの。百種類以上の酵母菌や乳酸菌が棲みつき発酵を続け、美味しいもろみを育んでいる。
見学自由のヤマロク醤油の蔵は、明治初期に建てられたもの。百種類以上の酵母菌や乳酸菌が棲みつき発酵を続け、美味しいもろみを育んでいる。
小豆島には古来より「最高の醸造容器」とされる木桶の蔵が数多く残るが、木桶仕込みは現在、国内醤油生産量のわずか1%未満に過ぎない。創業150年近いヤマロク醤油では、この日本の基礎調味料の本物を未来へ残すため、全国でただ一軒となった桶屋に修行に入り、木桶職人を復活させるプロジェクトに挑戦している。


上/「醤の郷」にある醤油蔵にふらりと立ち寄る。下/「マルキン醤油記念館」でもろみ絞り体験。
 「マルキン醤油記念館」で記念写真をパシャリ。
「マルキン醤油記念館」で記念写真をパシャリ。
1987年、マルキン醤油の創業80周年を記念して、国の登録有形文化財にも指定されている
国内最大規模の合掌造り建物を改装し、記念館として一般公開。しょうゆ造りの歴史や
製造方法を昔の道具やパネルを使ってわかりやすく紹介している。
発酵の島で作る日本酒を堪能する
 濾過を抑え個性を残す酒造りで、絞ったままのほんのり山吹色をした酒が並ぶ。
濾過を抑え個性を残す酒造りで、絞ったままのほんのり山吹色をした酒が並ぶ。
発酵の島と言われる小豆島で訪れたいのが、島内唯一の酒蔵「小豆島酒造MORIKIN」。2015年に蔵を立ち上げ、実に35年ぶりに島の地酒を復活させた。
看板商品は、島のオリーブから採取した「さぬきオリーブ酵母」で仕込む日本酒。果実を思わせる香りとトロピカルな酸味が特徴で、国内外の酒好きから注目を集めている。
杜氏には、兵庫・但馬地方出身のベテランを招聘。伝統的な寒造りの技術も守りながら、小豆島の温暖な気候に合わせた造りを実践している。
 気になる日本酒は試飲可能。これを目当てに毎年訪れるファンも少なくない。
気になる日本酒は試飲可能。これを目当てに毎年訪れるファンも少なくない。
 敷地内にはカフェやベーカリーも併設。カフェでは酒造りの副産物である吟醸粕を使った具だくさんの粕汁や、地元の食材を盛り込んだ「杜氏のまかない飯」(1,700円、ベジタリアン・ヴィーガン対応は2,200円)や甘酒スムージー(1,000円)など、発酵の恵みを堪能できるメニューが揃う。
敷地内にはカフェやベーカリーも併設。カフェでは酒造りの副産物である吟醸粕を使った具だくさんの粕汁や、地元の食材を盛り込んだ「杜氏のまかない飯」(1,700円、ベジタリアン・ヴィーガン対応は2,200円)や甘酒スムージー(1,000円)など、発酵の恵みを堪能できるメニューが揃う。
觜崎屋本店
たつの市龍野町下川原68-1-1
9:00 - 18:00
発酵Lab Coo
住所:兵庫県たつの市龍野町下川原 22−2
TEL:090-4292-5917
営業時間:10:00-17:00
定休日:不定休
体験料:1人につき2,200円
申し込み:090-4292-5917
足立醸造(直営店)
住所:兵庫県多可郡多可町加美区西脇81-1
TEL:0120-35-1381
営業時間:9:00-17:30
定休日:無休
URL: https://adachi-jozo.co.jp/
Instagram:
https://www.instagram.com/adachi_jozo?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==
ヤマロク醤油
マルキン醤油記念館
https://marukin.moritakk.com/kinenkan/
小豆島酒造MORIKIN