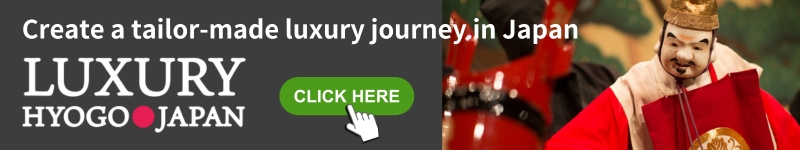- 自然・風景
- 歴史・文化
- グルメ
- 伝統・郷土芸能
No.f_0031
陰影の美を巡る湯けむりと古都の旅
日本文学を代表する作家・谷崎潤一郎は、随筆『陰翳礼讃』(1933年)で、日本建築や生活文化に潜む「影の美」を鮮やかに描いた。月の光に木立の影、障子越しの淡い光や漆器に映る陰影にこそ、日本の美の本質があると説き、その思想は今も多くの人を魅了し続けている。
谷崎の美意識を形づくった舞台のひとつが、古都・京都。寺院や庭園に息づく陰翳の美が、彼の文学世界を深めた。そして彼が足繁く通った温泉地が、兵庫の有馬温泉だ。
京都・嵐山と古泉・有馬温泉が誘う、光と影が織りなす陰影の美を辿る旅へ──。
世界遺産の名刹で”侘び寂び”の真髄に触れる。
 本堂に当たる大方丈からの眺め。
本堂に当たる大方丈からの眺め。
京都市街地から電車で約20分。古都の西に広がる嵯峨・嵐山エリアは、四季折々の豊かな自然と、光と影が織りなす美の舞台である。その風景の中に静かに佇む「天龍寺」は、暦応2(1339)年に、足利尊氏が後醍醐天皇の菩提を弔うために創建し、禅僧・夢窓疎石が開山。1994年には世界遺産に登録された名刹だ。
夢窓疎石によって築かれた「曹源池庭園」は、その周囲を歩きながら角度によって変わる景色を楽しむ池泉回遊式庭園として知られるが、本来は修行僧が夜ごとに座禅を組み、心を磨くために築かれた座観式庭園が原点である。縁側に腰を下ろし、目線の高さに広がる景色と向き合うとき、その真髄に触れられる。
 書院から眺めた大方丈と庭園。池が水鏡となり、嵐山の自然を映す。
書院から眺めた大方丈と庭園。池が水鏡となり、嵐山の自然を映す。
夢窓の教えに、「山水には得失なし、得失は人の心にあり」という有名な言葉がある。山や水、木々そのものに美しさは宿らず、それを美しいと感じるかどうかは見る者の心次第である。庭を見て美しいと感じるなら、それはあなたの心が清らかである証。逆に心が荒んでいれば、この庭もまた荒んで見えるだろう。ゆえにこの庭は、心を浄化へと導く場なのである。
 法堂の天井に描かれた「雲龍図」。土日祝日・特別公開期間に限り拝観できる。
法堂の天井に描かれた「雲龍図」。土日祝日・特別公開期間に限り拝観できる。
法堂の中に一歩足を踏み入れると、庭園とは異なる静謐な空間が広がる。天井に描かれた「龍雲図」は、どの角度から見ても視線を向ける“八方睨みの龍”。その力強さと柔らかさが同居する姿は、まるで天と地、光と影、動と静を一度に体感させてくれるかのようだ。そしてその眼差しは、私たちの内に潜む光と影までも映し出す。
美しい陰影が揺らめく、竹林の小径を歩く。
 野宮神社から大河内山荘へ抜ける全長約400mの「竹林の小径」。
野宮神社から大河内山荘へ抜ける全長約400mの「竹林の小径」。
天龍寺の北門を抜けると、嵐山随一の名所「竹林の小径」が広がる。天を衝くように伸びる無数の竹の間からは柔らかな光が降り注ぎ、風が吹けば竹の葉がささやき、木漏れ日が揺らめく。谷崎潤一郎は随筆『陰翳礼讃』で讃えた、光と陰が織り成す美――その余韻を、この小径は今も静かに伝えている。
太古の海の化石水と言われる有馬の湯
 有馬で最も古い宿「御所坊(ごしょぼう)」の湯。金泉が湧き出る源泉掛け流し。屋内は男女別で、その先が半露天になっている。
有馬で最も古い宿「御所坊(ごしょぼう)」の湯。金泉が湧き出る源泉掛け流し。屋内は男女別で、その先が半露天になっている。
 金泉は湧き出した直後は無色透明だが、空気に触れると鉄が酸化し赤褐色へと変わる。
金泉は湧き出した直後は無色透明だが、空気に触れると鉄が酸化し赤褐色へと変わる。
京都の旅の疲れを名湯で癒す。京都・大阪・奈良の三都から有馬温泉へは、電車かバスを利用して1時間から1時間半程度。有馬温泉は、日本書紀や風土記にも記される日本最古級の温泉で、白浜・道後と並ぶ「日本三古湯」の一つ。太閤・豊臣秀吉がこよなく愛したことでも有名で、太閤ゆかりの名所や石碑が今も点在する。
長い歴史の中で文人墨客も数多く訪れた有馬、谷崎もその一人だ。
 金泉が湧き出る「御所泉源」。湯気がもくもくと立ち上る。
金泉が湧き出る「御所泉源」。湯気がもくもくと立ち上る。
有馬といえば、赤褐色に濁った「金泉」。日本の温泉の多くは火山活動によって生まれるが、有馬温泉は非火山性の温泉。地下深くにしみ込んだ太古の海水が、数百万年もの時を経て地殻変動の熱や岩石に触れ、成分を変化させながら地表へと湧き上がっている。いわば「地球の記憶」を宿した湯であり、その由来から「太古の海の化石水」とも呼ばれる。
効能は、鉄分と塩分がもたらす強い保温効果。湯に浸かったあとは、まるで肌に薄い膜が張ったように熱が逃げにくく、湯上がりの身体は長く温もりを保つ。冷え性や神経痛、関節痛に効果があるとされ、「熱の湯」として古くから人々に愛されてきた。
金泉の源泉をもっとも気軽に楽しめるのが、温泉街のちょうど真ん中にある公共浴場「金の湯」(入湯料:大人800円)だ。地元の人と観光客でにぎわい、無料で浸かれる足湯もある。
近代に入ると、医学的な視点から炭酸泉やラジウム泉の効能が注目されるようになり、無色透明でさらりとした湯ざわりの銀泉も人気を集めるようになった。「金泉」が体の外側からじんわり温めるのに対し、「銀泉」は血流を促し、体の内側に効く湯といわれている。
おすすめは、まず金泉で体を芯まで温め、そのあとに銀泉に浸かって血行を促す入り方。二つの湯を交互に楽しむことで、発汗作用やリフレッシュ効果がより実感できる。趣の異なる湯めぐりを目当てに、金泉・銀泉をはしごする観光客も多い。
有馬の宿泊の予約
旅の記念に伝統工芸の有馬筆はいかが
 筆を手に持ち字を書こうとすると、筆尻から仕込まれた豆人形がひょこっと顔を出す。
筆を手に持ち字を書こうとすると、筆尻から仕込まれた豆人形がひょこっと顔を出す。
温泉地という人々が行き交う場所で育まれた伝統工芸がある。約1400年前に、子どもができないことを嘆いていた孝徳天皇が、有馬温泉に逗留してまもなく有間皇子が誕生したという故事にヒントを得て、室町時代(1336年〜)に人形師の伊助が考案したのが「有馬人形筆」。江戸時代(1600~1800年代)には「有馬筆」「奈良筆」「江戸筆」と並び称され、日本三筆のひとつに数えられた。
特徴は「腰の強さ」と「穂先のまとまり」。弾力があるため線に強弱を出しやすく、細やかな文字も美しく書ける。
 現在、「有馬筆」の工房は「灰吹屋(はいふきや) 西田筆店」のみ。店内では目の前で、筆を仕立てる手仕事を見ることができる。
現在、「有馬筆」の工房は「灰吹屋(はいふきや) 西田筆店」のみ。店内では目の前で、筆を仕立てる手仕事を見ることができる。
 広島・熊野の化粧筆を、京都・西陣で染めてもらった絹糸で日本の伝統柄に巻き上げる。1本4,000円から。
広島・熊野の化粧筆を、京都・西陣で染めてもらった絹糸で日本の伝統柄に巻き上げる。1本4,000円から。
 店舗がある長屋の2階は「有馬小宿 八多屋」があり、気軽に泊まれる素泊まりの宿として人気。
店舗がある長屋の2階は「有馬小宿 八多屋」があり、気軽に泊まれる素泊まりの宿として人気。
「金の湯」の向かいにある「有馬玩具博物館」1階の「おもちゃ工房」では、参加費5,000円で、有馬人形筆からくり工作体験が実施されている。
温泉街に息づく雅な文化「有馬芸妓」
 「芸妓カフェ一糸(いと)」の舞台にて。
「芸妓カフェ一糸(いと)」の舞台にて。
江戸時代から明治・大正(1603年から1926年頃)にかけて、温泉街の社交の場を華やかに彩ってきたのが有馬芸妓。有馬芸妓は、関西唯一の本格的な芸妓文化が残る温泉芸妓で、京都の花街や大阪の北新地と並び称される存在だ。
 現在も全国各地の宴席や公式行事に出張し、日本舞踊や端唄、小唄を披露している。
現在も全国各地の宴席や公式行事に出張し、日本舞踊や端唄、小唄を披露している。
 芸妓が有馬の街を練り歩くだけで、情緒的な景色に色を添える。
芸妓が有馬の街を練り歩くだけで、情緒的な景色に色を添える。
 カフェの人気メニューはお抹茶と和菓子のセット(1,800円)。
カフェの人気メニューはお抹茶と和菓子のセット(1,800円)。
有馬芸妓の踊りやお座敷あそびが体験できる「芸妓カフェ一糸」では、敷居の高いイメージがあった芸妓の踊りやお座敷あそびを気軽に楽しめる。芸妓踊りの観覧料は1,500円、現役芸妓に着付け・ヘアメイクをしてもらう有馬芸妓変身スタイルは33,000円。
雅な芸妓文化に触れることで、温泉町の風情を実感できるはず。
 味はプレーン(350円)、抹茶、ショコラ(各400円)の3種。ペアリングには爽やかな無添加ぶどうジュース(650円)を。
味はプレーン(350円)、抹茶、ショコラ(各400円)の3種。ペアリングには爽やかな無添加ぶどうジュース(650円)を。
2025年4月に開店したフィナンシェの店「Coccinelle(コチネレ)」は、芸妓・一菜さんのお気に入りの店。無添加・グルテンフリーで自家製の米粉を使った生地は、表面はサクッ、中はもっちり。食べ歩きできるサイズなので、有馬散策のお供にぴったり。
谷崎が愛した有馬温泉最古の宿
 「御所坊」のフロント。館内には、物語のある漢詩の作品が展示されている。
「御所坊」のフロント。館内には、物語のある漢詩の作品が展示されている。
「御所坊」の創業はおよそ800年。有馬温泉最古の宿で有馬の中心に位置し、有馬の歴史とともに歩んできた存在だ。
木造建築の深い庇、障子越しに射すやわらかな光、石畳の庭……。館内には谷崎が随筆『陰翳礼讃』で讃えた「影の美」がそこかしこに息づいている。照明を抑え、静謐な空気を大切にしたしつらえは、どこか懐かしく、それでいて洗練された趣。まさに「陰翳の美」を体感できる空間になっている。
 縁側と和室、洋室が備わる「RAKU」。1泊1名2食付き(2名1室利用時)で3万9,400円〜。
縁側と和室、洋室が備わる「RAKU」。1泊1名2食付き(2名1室利用時)で3万9,400円〜。
![]()

この宿で、滝川のせせらぎの音に耳を傾けながら、時の文豪たちは数々の名作を生んだ。
御所坊の一室「RAKU」は、谷崎が生前、御所坊に滞留し、小説を書き上げた当時の雰囲気を再現した部屋。客室内には、谷崎関係の本や書、三田青磁が展示されている。

 夕膳のコースは、先付け、寄り盛、お造り、焼き物、揚げ物、肉料理、デザートなどの会席料理。
夕膳のコースは、先付け、寄り盛、お造り、焼き物、揚げ物、肉料理、デザートなどの会席料理。
関西の奥座敷と言われる有馬には、時の天皇や将軍などが保養に訪れていた。その時のもてなしで生まれたのが、自然の素材を生かした素朴で野趣あふれる「山家(やまが)料理」だ。「御所坊」の食事は、山里の四季を映した「飾らない、自然の恵みをそのままいただく」スタイルで提供される。
 丹波にある「西山酒造」と一緒に作ったクラフトジン「ヒョウゴ・ヴィ・ジン」。但馬のワサビ、丹波のブルーベリー、播磨のゆず、摂津の有馬山椒、淡路の鳴門オレンジと、兵庫の5地域の名産を使用。エリアごとに個性豊かな兵庫を一つにした味わいは、ピリッとスパイシーだ。
丹波にある「西山酒造」と一緒に作ったクラフトジン「ヒョウゴ・ヴィ・ジン」。但馬のワサビ、丹波のブルーベリー、播磨のゆず、摂津の有馬山椒、淡路の鳴門オレンジと、兵庫の5地域の名産を使用。エリアごとに個性豊かな兵庫を一つにした味わいは、ピリッとスパイシーだ。
温泉文化と文学、グルメ、そして歴史が交差する温泉地であることが、有馬の一番の魅力といえる。
湯けむりと古都で見る陰影。光と影を手がかりに歩く旅は、ただの観光を超えて、日本文化の深層へと導いてくれる。
有馬の宿泊の予約
(掲載スポット)
天龍寺
竹林の小径
https://kyoto.travel/en/areas/saga-arashiyama/
https://kyoto.travel/fr/areas/saga-arashiyama/
https://kyoto.travel/es/areas/saga-arashiyama/
https://kyoto.travel/cn/areas/saga-arashiyama/
https://kyoto.travel/tw/areas/saga-arashiyama/
https://kyoto.travel/ko/areas/saga-arashiyama/
金の湯
https://arimaspa-kingin.jp/kin-01.htm
灰吹屋(はいふきや) 西田筆店
有馬小宿 八多屋
有馬玩具博物館
芸妓カフェ一糸
Coccinelle
https://www.instagram.com/coccinellearima/
御所坊
西山酒造場