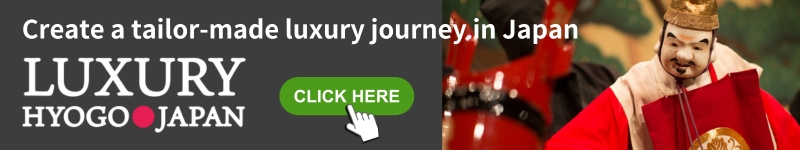- 歴史・文化
- 伝統・郷土芸能
No.f_0029
白と赤のジャパンカラーを巡る旅
清浄、神聖、再生の色とされ、儀式や祝い事に欠かせない白。太陽、血、命の象徴であり、五穀豊穣を祈る赤。兵庫県赤穂市と姫路市を舞台に、日本文化の根底をなす白と赤、そこに宿る日本人の美意識を巡礼する。
平和を祈り尊ぶ、姫路の白
 陽を浴びて輝く白壁。
陽を浴びて輝く白壁。
姫路の白といえば、「白鷺城」の名をもつ姫路城だ。
1600年の関ヶ原の戦い後、池田輝政は羽柴秀吉が築いた姫路城を大改築し、新たに連立式天守を築いた。続く本多忠政により西の丸と三の丸が造営された。以来400年以上もの間、戦火などによる損壊を免れてきた不戦・不焼の城は、良好な保存状態と優れた木造建築であることが評価され、1993年に世界遺産に登録。街のシンボルであり誇りでもある。
 姫路駅からの眺め。
姫路駅からの眺め。
姫路城が「白鷺城」と呼ばれるのは、「白漆喰総塗籠(しろしっくいそうぬりごめ)」という技法によって外壁だけでなく屋根瓦の目地にも白漆喰が施された姿が、飛び立つ白鷺に見えることから。漆喰には防火、防水の役割があるが、当時の城主だった池田輝政が、戦国時代の終わりの象徴として白にしたという説もある。時代を経て、太平洋戦争中は空襲を免れるために黒い擬装網がかけられていた姫路城。戦後に擬装網が取り払われて現れた白い姿は、市民にとって平和の到来の合図だったという。
姫路駅に降り立つと、街の平和を見守る姫路城の姿を見ることができる。
姫路の宿泊の予約
純白のミネラルは瀬戸内海の恵み
 「赤穂の天塩海洋科学館・塩の国」では塩職人衣装も試せる。
「赤穂の天塩海洋科学館・塩の国」では塩職人衣装も試せる。
体にも生活にも欠かせない白いミネラル、塩。
岩塩が採れない日本では、古来より海水を原料とする塩づくりが行われている。瀬戸内海と千種川がつくる広大な干潟と晴れの日に恵まれた赤穂は、塩田に絶好の地。1645年に潮の干満差と太陽熱を利用した「入浜式塩田」が大規模開拓されて以来、「塩の国」として名を馳せた赤穂は、製法が変わった今も全国需要の7分の1の製塩を担っている。
 入浜塩田の奥にあるのは、かん水をつくる竹製装置。
入浜塩田の奥にあるのは、かん水をつくる竹製装置。
 かん水を大釜で煮詰めて塩ができる。
かん水を大釜で煮詰めて塩ができる。
赤穂の自然と人の知恵が育んだ塩づくりは、日本遺産に登録されている。その歴史や技術は、塩田跡地に建つ「赤穂の天塩海洋科学館・塩の国」(入館料は大人200円、小人100円)で見学、体験できる。ここでは、かつての塩田風景が再現されているだけでなく、さまざまな時代の塩田が復元され、実際に瀬戸内海の海水を使った塩づくりが行われている。
 塩づくり体験で見る塩の結晶。
塩づくり体験で見る塩の結晶。
 約250mlのかん水から約45gの塩ができる。
約250mlのかん水から約45gの塩ができる。
入館者の塩づくり体験は無料。目の前の塩田でつくられた「かん水」(塩分濃度を高めた海水)を土鍋に入れてかきまぜながら煮詰めていくと、5分ほどで純白の塩があらわれる。海水を濃い塩水に濃縮したものを煮詰めて塩の結晶を取り出すという製塩方法は、技術的には進化しているが、原理は昔から変わらない。
できあがった塩は、にがりを除去していないため、ミネラルを豊富に含むまろやかでコクのある味わい。来館記念でもらえる塩との味くらべも楽しめる。
海と森の栄養が育む海のミルク
 身がふっくらした坂越かき。
身がふっくらした坂越かき。
赤穂の海がもたらすもうひとつの白いミネラルが、「海のミルク」といわれる牡蠣。
瀬戸内海に大きく開いた坂越湾は、原生林が茂る神域の生島や千種川からの栄養が合わさった豊かな漁場。ここで養殖される「坂越かき」は1年という短期間で育つことから、「一年牡蠣」の名をもつ。身が大きくぷりぷりでふっくらし、おいしく食べられることが魅力だ。
 坂越の町並み。
坂越の町並み。
坂越のメインストリートは白い石畳の「坂越大道」。港町として栄えた江戸時代からの風情を今に伝える。その通りにある「伝馬船」は、坂越牡蠣を生産する「大河水産」の直営店。新鮮な坂越かきを味わえる。
 三種の味付けで食べる生牡蠣。
三種の味付けで食べる生牡蠣。
 千種川の水と播磨の酒米を使ってつくられた地酒は、坂越かきのペアリングに最適。
千種川の水と播磨の酒米を使ってつくられた地酒は、坂越かきのペアリングに最適。
生牡蠣はクリーミーな甘さと磯の香り、蒸牡蠣は凝縮したうまみを味わえる。どちらも苦味がなく、牡蠣が苦手な人でもおいしく食べられる。店舗の向かいにある酒蔵「奥藤商事」の地酒3種との利き酒セット(1,000円)も人気。地酒は坂越牡蠣に合う、力強い酸味のある「忠臣蔵 生酛純米雄町」、甘口でまろやかな「吟醸 乙女」、ワインのような香りの「忠臣蔵 純米吟醸 47キャトルセット」が並ぶ。
牡蠣はうまみや栄養をたっぷり含むだけでなく、「福を“かき”込む」縁起物でもあるといわれている。食べて、健康と運気のアップを期待したい。
夕焼けを映し出す赤穂雲火焼
 桃井香子さん作の水指。
桃井香子さん作の水指。
赤は、「赤穂雲火焼」にある。
赤穂雲火焼は、1852年に大嶋黄谷(おおしま こうこく)が赤穂で生み出したやきもの。赤と黒のグラデーションが織りなす紋様は赤穂の夕日を連想させる。黄谷が技法を伝えることなく生涯を閉じたため、「幻の焼き物」とされていたが、作品に魅了された陶芸作家の桃井香子(ももい よしこ)さんと長棟州彦(ながむね くにひこ)さんが、30年の歳月をかけて再現に成功。陶土は赤穂のなめらかな土。釉薬を使わずに焼き、赤くしたいところには炎を、黒くしたいところには煙を当て、色を出していく――。こうして、再び赤穂雲火焼の歴史がはじまった。
 赤穂雲火焼の唯一無二の絵柄。
赤穂雲火焼の唯一無二の絵柄。
赤穂御崎を一望できる「桃井ミュージアム」では、赤穂雲火焼の展示販売を行うほか、赤穂雲火焼の塩壺づくり体験(2人以上で受付。1人5,500円、送料別)も実施している。講師は、ミュージアムの支配人であり陶芸作家の長棟光亮(ながむね みつあき)さん。州彦さんの息子でもある光亮さんは、「幻だった赤穂雲火焼が、いろんな人の手から生まれるようになったことがうれしい」と話す。
 塩壺は手びねりでつくる。
塩壺は手びねりでつくる。
 体験中。仕上げに模様入れ。塩壺なので「しお」。
体験中。仕上げに模様入れ。塩壺なので「しお」。
 焼成された塩壺は1〜2カ月後に届く。
焼成された塩壺は1〜2カ月後に届く。
釉薬を使わない素焼きの赤穂雲火焼は湿気を吸ってくれるため、塩をサラサラの状態に保ってくれる。「再生」の意味をもつ白は、赤穂雲火焼にぴったりの色。どんな赤が出るかは焼成された作品が届いてからのお楽しみだが、塩とのコントラストは美しいはず。
 日本夕陽百選の岬・赤穂御崎。
日本夕陽百選の岬・赤穂御崎。
赤穂での最後の楽しみは、赤穂御崎から眺める夕日。空と海を赤く照らしながら瀬戸内海に浮かぶ島々の向こうに沈んでいく夕日は、荘厳で神秘的。見慣れている地元の人も思わず足を止めて見入ることもあるとか。赤穂雲火焼の祖である大嶋黄谷も、この景色に魅せられたのかもしれない。
赤穂の宿泊の予約
(掲載スポット)
姫路城
https://www.city.himeji.lg.jp/castle/
赤穂の天塩海洋科学館・塩の国
伝馬船
https://www.instagram.com/tenmasen_oyster/
桃井ミュージアム